日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】
製造業
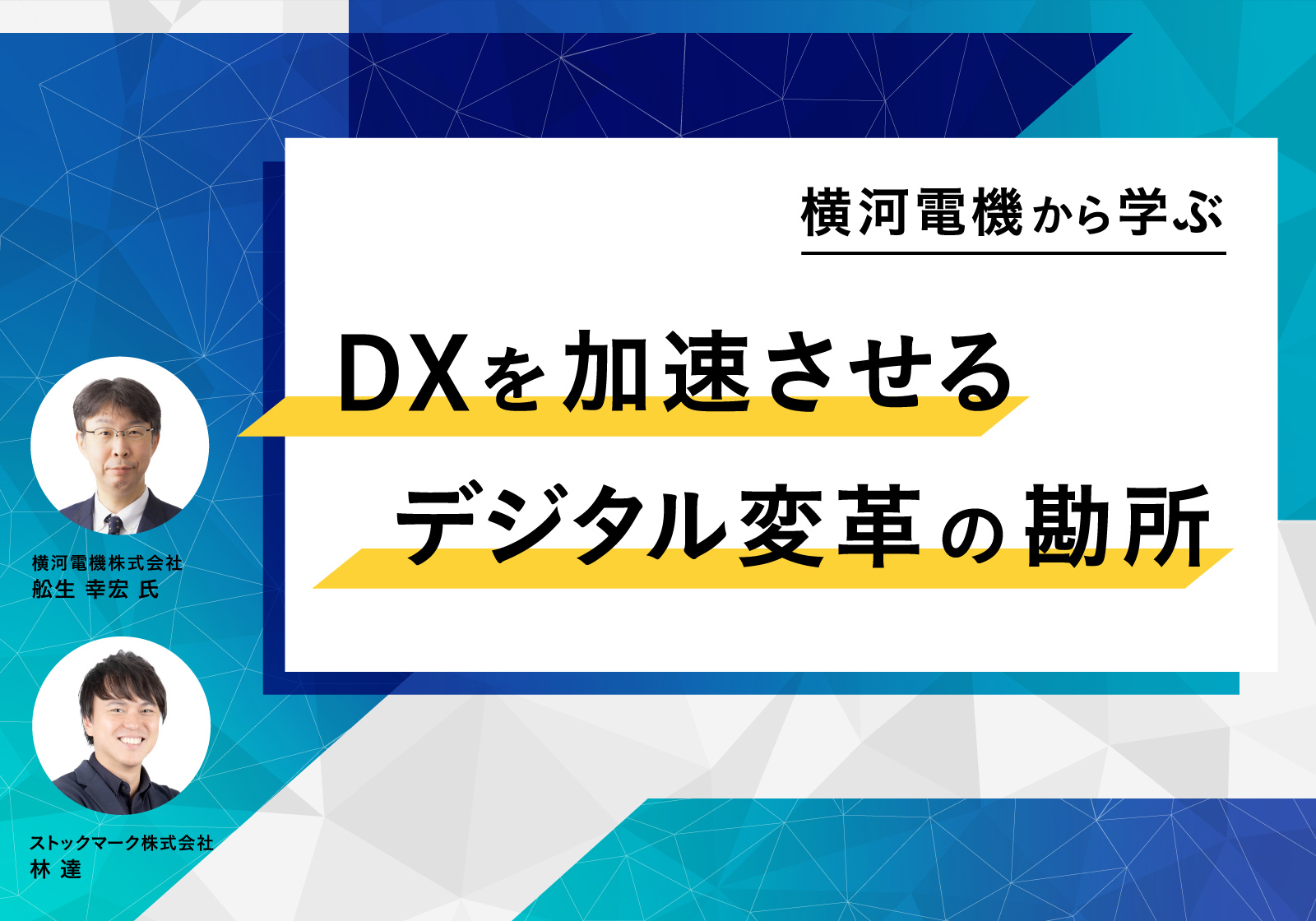
ここ数年、DXのマーケットは大きな変化を見せている。だがその一方で、多くの企業でDXに未着手、またはほとんど進展していない現状がある。DXの推進において特に大きな障壁となっているのは、新しいことを受け入れにくい企業風土だ。デジタル技術への理解や、他部門と円滑に協働するにはどのようにしたらいいのだろうか。
今回は「豊かな人間社会の実現に貢献する」ことを企業理念とし、「計測」や「制御」、「情報」をビジネステーマとする横河電機株式会社(以下、横河電機)の、舩生(ふにゅう)幸宏氏にお話を伺った。デジタル戦略本部長として社内の DX を推進する一方、デジタルソリューション本部の DX プラットフォームセンター長として顧客に対しての DX の双方を管掌する取り組みとはどのようなものなのだろうか。
※当記事は2021年4月15日に開催したオンラインセミナーの内容をもとに作成しています。
目次
舩生氏は大学の経済学部を卒業後、当時趣味として触れていたパソコンからIT分野に興味を持ち、ITの道を目指し株式会社NTTデータに入社。顧客に対するソリューションサービスとして金融システムの開発と運営に携わった。ここで開発者として働くうちに、システムがビジネスにどう使われるかという部分に強く興味を抱くようになる。
そして、ソフトバンクファイナンス株式会社(現SBIホールディングス株式会社)に移り、金融機関を顧客としてB to Cのインターネット金融サービスのローンチを手掛けるようになる。やがて舩生氏は日本の強みである製造業にも興味を抱き、日本が世界で勝負できる土壌で働きたいとソニー株式会社に移った。その後2018年に横河電機に入り、ここでB to Bの製造業に足を踏み入れることとなる。
横河電機のDXの取り組みは、大きく分けて2種類。デジタルによって業務プロセスを変革することや、ITインフラを強化する成長基盤を確立する生産性向上のためのDX。同社流に呼ぶと「インターナル DX」だ。もう一つはお客様へデジタルサービスを提供するための「エクスターナル DX」。この二つのDXを組みわせて成長機会創出と成長基盤の確立の実現を目指している。
この二つのDXは組織としては分かれているとのことだが、舩生氏は双方を兼務している。「たまたま兼務することになった」と舩生氏は言うが、氏の経歴は現在の兼務が偶然ではないことを物語っている。ソニー株式会社の情報システム部門でインターナルDXに尽力し、株式会社NTTデータでのITを活用してお客様に対するITソリューションビジネスや、ソフトバンクファイナンス株式会社でのB to Cのインターネット金融サービスの立ち上げは、エクスターナルDXだったと舩生氏は振り返った。舩生氏は3社で積み重ねてきたエクスターナルDXとインターナルDX双方の経験を複合的に生かしながら、現在の職務に当たっている。
横河電機の強みは、Operation Technology(OT)と呼ばれるデバイスとその制御システムである。現在、どのような領域においても、デジタル化を進める上でハードウェアのデバイスは必須であり、特にB to Bビジネスの場合は、デバイス製造事業は大きな戦力になる。この点で横河電機には製造業として高いポテンシャルがあるが、一方で、デバイスだけでは「製品の販売」で終わってしまう。
OTはデジタルサービスと組み合わせることによって真価が発揮される。商品や製品を作ることだけではなく、デジタルを活用したサービスを創ること、それは横河電機だけでなく製造業全体が課題とする分野である。その課題の部分を補うことで、豊かな人間社会の実現に向けて、デバイスなどの製品×デジタルサービスでの相乗効果をもたらすことができるであろう――舩生氏はそう語る。
舩生氏が横河電機に移った2018年、氏は最初の3カ月を費やして、ビジネス部門のトップにヒアリングを行った。そして、DX推進における最大の課題を確信した。多くの企業と同様、横河電機でもサイロがDX推進の障壁となっていたのだ。サイロに阻まれて社内での情報流通ができておらず、同じ会社でありながらシステムやオペレーションは部門ごとにバラバラ。さらに、必要とされればそれらを人の作業で橋渡ししなければいけない。
サイロ化の問題を解消するために舩生氏が力を注いだのが、データの統合だった。「DXの1丁目1番地はデータ統合」と舩生氏は主張する。いかに社内システムの数を減らしてデータを統合するのか。舩生氏は、これらの目標を「会社のDXの足元を固める」ための最初のステージと位置付けた。データが統合されていなければ、AIがどれほど充実したところでAIの価値は発揮されない。
同社のDX実現に向けたIT中期計画(2018年度-2020年度)は4つの柱で構成されている。一つめが、ITのグローバル化を目指す「グローバル最適化」。二つめは「デジタル化/サービス化」。デジタル化を進めることで、製造業がサービス化するため、デジタル化とサービス化は対になっていると言う。三つめが、様々なものがデジタルで繋がることへの守りの確保として「セキュリティ強化」。四つめが、IT部門全体を先見的なものにする、すなわちIT部門を社内変革の機動力に変えていくための「IT Transformation」を軸としている。
この計画において、舩生氏は「グローバル最適化」と「IT Transformation」を同時に進めた。グローバル最適化を目指すためには、まずはIT自体が世界に通用するものとなっている必要がある。「グローバル最適化とITのグローバル化は、表と裏の関係」と舩生氏はそう説明する。DX推進に対する舩生氏の姿勢は、氏の企業観と決して無縁ではない。企業とは「売り上げを上げる傍らでコストが発生する。その差で利益が出る」。このフローにおいて、IT部門は「お金を使わせていただいている側」だ。したがってIT部門がいかにコストを最適化できるか。その結果、会社の売り上げに貢献できるか。その姿勢や体制が大事になってくる。舩生氏はビジネス部門との連携についても重要視している。利益を出すという同じ目標に向かって、ビジネス部門とIT部門と言うそれぞれの専門集団が協力していかに共に創り上げることができるかだと言う。
とはいえ、各部門の理解と協力をどのようにして促進していくのか。横河電機の課題は、多くの企業もまた共通に抱える悩みである。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、DXの推進にもっとも遅れが見られるのは「企業文化や組織マインドの根本的な変革」領域での取り組みであった。また、民間調査会社の IDC による報告でも、DX 推進の一番の阻害要因として、従業員一人一人の受容性が低い点が指摘されている。他部署との共創のためのポイントは「DXをやってる主体がでしゃばらないことだ」と舩生氏は考える。最終的なビジネスベネフィットを達成するのはビジネス部門であり、あくまでもその部門が主役であると言う。
DXを進める上で、他部門のメンバーにデジタル化の必要性や理解を得ることは必須である。デジタルリテラシーを上げていくには、「体感」がカギであると舩生氏は説く。IT部門がどれほど言葉で説明したところで、ビジネス部門おのずから「このシステムは便利そうだ。これを自分で使って実際にビジネス効果を上げたい」と思わなければDXは進まない。実際に見たり触ったりして体感したいのが人間であり、この「体感」をいかに増やしていくかが重要なのだと言う。IT部門から言われてやらされている、そんな意識のままではビジネスメリットは生み出せない。ビジネスのフロントに立つビジネス部門がいかに主役として「体感」するか、そのためにIT部門はいかに黒子に徹せられるか。この関係性をうまく保てるかどうかが勝負だと、氏は力説する。
例えばTableau。現在、社内では導入が進んでいるが、当初は実際にダッシュボードを作成し、舩生氏が役員全員に見せて回ったという。ダッシュボード上で、データがいろいろなグラフに可視化され、リアルタイムで数字が変わっていく様子を目の当たりにして、皆「なるほど」と感じていたそうだ。Tableauの活用は、コロナの流行で一層進んだ。便利なツールとそのメリットを「体感」することが人間のやる気につながるのでは、と氏は話す。
データ統合はIT部門で進めたが、その先のデータを活用してビジネスに反映していく必要がある。そのために全従業員がツールなどを活用し自分なりの分析ができるようになること、その上で積極的にビジネスに生かせるようになることを目指し、研修やトレーニングにもかなり力を入れてきた。その結果、ここ3年ぐらいで、従業員の間には新しいものも抵抗なく受け入れる土壌ができていると言う。
また全従業員にIT部門の状況を理解してもらうために、毎年上期と下期で2回発行している『ITレポート』で、IT部門の活動概要を発信している。また、最近始めた取り組みに、Teamsを使ったウェビナー形式の説明会がある。ここでは、従業員に向けてDXの現況と今後の展望について説明している。これまでの横河電機では、一つの部門、特にIT部門が全従業員向けにこのような活動報告を行うということがなかったため、皆が新鮮に受け止めているそうだ。一方では厳しい意見もあるが、舩生氏はこれらを絶好の改善の機会と捉えている。
「体感」は、インターナルDXとエクスターナルDXを両輪で加速させていくことにも多いに役立つと言う。実際、ビジネスとしてのDXとコストセンターとしてのDXは、方向性としてはかなり異なる活動であり、多くの企業ではいかにバランスをとって進めていくかが課題となっている。ここで舩生氏は、インターナルDXの推進を「体感」のタネとして活用している。すなわち、新しく顧客サービスを作る際に、社内のインターナルDXでまず試すのだと言う。
舩生氏のロジックはこうだ。インターナルDXは社内においてはコストセンターなので、ある程度資金が使える。そこで、まず社内向けのサービスに投資して、そのサービスを実際に従業員に使ってもらう。この時、「このサービスはかなり良い」という評価がつけば、社外に出せると判断する。投資をして社内で使うだけでは「コスト」で終わってしまうが、それが社外に売り出せるとなれば、利益につながりコストも回収でき、ビジネス貢献もできる。社内のIT投資を投資で終わらせずに、従業員の「体感」に基づいてビジネス化するというわけだ。こういった事例はまだ道半ばと舩生氏は言うが、いくつか成功事例が生まれつつあり、もっと増やしていきたいと希望を膨らませている。
舩生氏がここ最近、ITメンバーに向けてよく口にしているのが「仕込み」と言う言葉だ。アジャイル開発とは言え、何かシステムを作るには数ヶ月などの時間がかかってしまう。そこで、次にどんな波が来るのかを予測し、ある程度PoCを進めておく、そして兆しが見えたときにはすぐに動けるようにしておく。こういった「仕込み」が、将来の業務において重要な足掛かりとなるのだそうだ。
「DXの取り組みの本質はサイロを壊す活動である」と舩生氏は強調する。DXの推進において、部門を超えたタスクフォースで活動することは、必然的にサイロを壊す活動になっているのだ。各拠点からアサインされたIT担当者たちが一つのチームとなり、オンライン化されたシステム上でさまざまな施策に取り組む。舩生氏はこのような改革的な横串のプロジェクトを増やすことで、サイロの最小化を目指している。
また、社内DXの推進過程で生じるのが、イノベーションとデジタル化の相性の問題である。たとえば、製造業ではオフラインの現場でディスカッションすることが、新しいアイデアの創出や暗黙知・経験知の共有につながるという意識が根強い。そのような意識のもとでも、いかにDXを進めていくことができるのか。舩生氏はブレインストーミングのような活動はオンラインミーティング、ウェビナーなどでは難しいことを認める。だが、現実の職務の8割は既存業務やその改善であり、新規性が求められるのは残りの1割~2割だという。DXの推進によって8割の部分をいかに効率化するか、その余力で2割の部分にいかにアプローチするか。舩生氏は今、その可能性を探っている。
今回は舩生氏に、
・一番大きな課題はサイロ化を抑え、データを統合すること
・他部署との共創のポイントはDX部署が黒子に徹すること
・デジタルリテラシーを上げるには「体感」が必要なこと
など、デジタル変革を進めていくためのヒントをお伺いした。
DXは、他部門を巻き込み全社的に進めるため、メンバーの理解が必要不可欠である。まずは横串のコミュニケーションを取りやすくするためにサイロを壊し、共創しやすい環境を整えることから始められてはいかがだろうか──。
