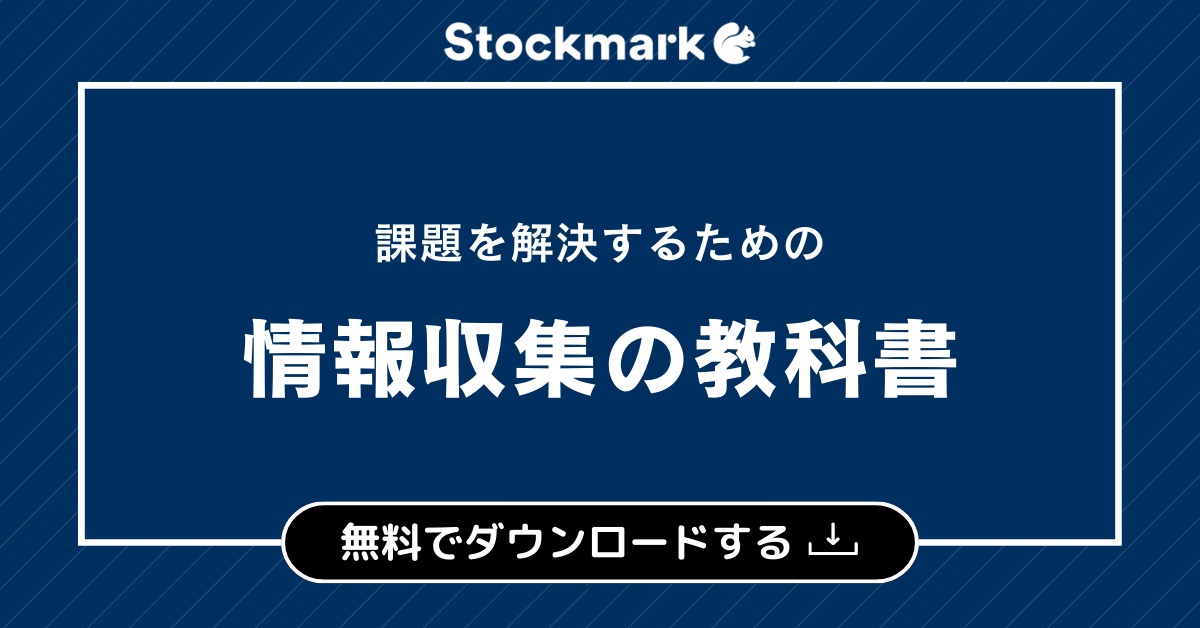日本や世界の半導体メーカー・会社・企業【分野別で紹介】
製造業
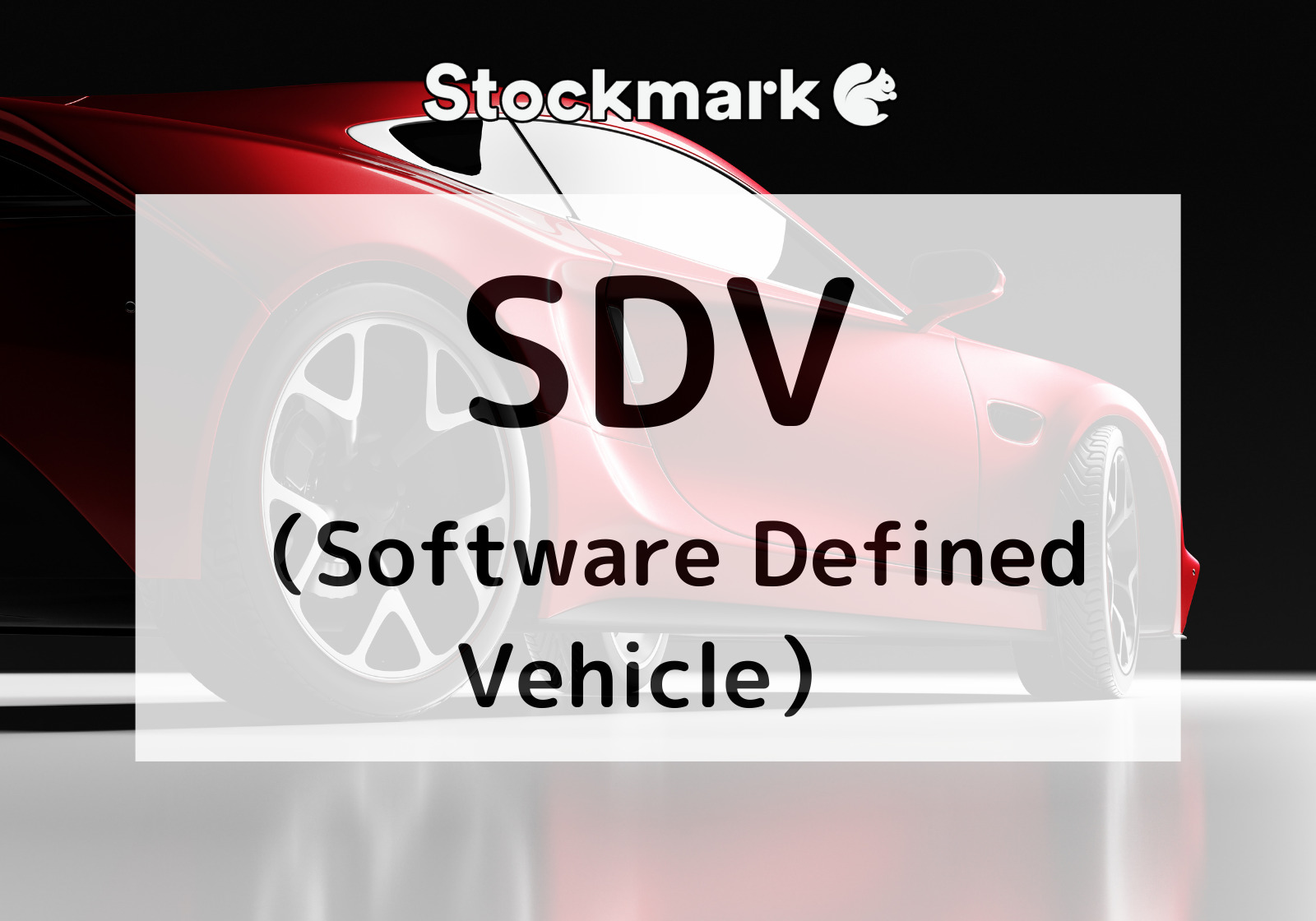
従来の自動車はハードウェアを中心に設計され、新機能の追加や改良には物理的な変更を必要とした。しかしながら、SDV(Software Defined Vehicle)の登場によってソフトウェアを更新するだけで機能拡張や性能向上が可能となり、自動車の概念そのものが変革しつつある。大手自動車メーカーに加え、GoogleやAppleなどのIT企業、さらには半導体メーカーなどもSDVの開発競争に参入しており、業界構造は刻々と変化を遂げている。本記事では、SDVの概要と市場動向、普及に向けた課題について詳しく解説したい。
技術課題の解決や、市場の動向を読み解くには?
誰も教えてくれない情報収集の基礎
「情報収集の教科書」を見てみる
目次
SDVとは、ソフトウェアによって定義される車両を指す。ソフトウェア・デファインド・ビークルとも。日本語では「ソフトウェア定義型自動車」と呼ばれる。
従来の自動車では、製造したら機能はほぼ固定化されていた。しかし、SDVは搭載されるソフトウェアの性能が自動車の性能を決定づけるだけでなく、スマートフォンなどのようにソフトウェアのインストールやアップデートで新機能を追加したり、既存の機能を改善したりすることができる。
なお、SDVの考え方はテスラによって生み出されたとされるが、まだ新しい概念であるため、どこを起源とするかは見解が分かれているのが現状だ。一説によると、2010年後期から2020年初頭にかけて誕生したとされる。

技術課題の解決や、市場の動向を読み解くには?
誰も教えてくれない情報収集の基礎
「情報収集の教科書」を見てみる
SDVは、ソフトウェアの更新を通じて車両の基本機能や性能を継続的に向上・改善させることを中心に据えている。コネクテッドカーは車両がインターネットや他のデバイスと接続され、情報の送受信や外部サービスとの連携を可能にした自動車のことを指す。近似した概念ではあるものの、あくまで外部サービスとの連携や情報提供に重きをおいている点でやや異なる。
CASEは、自動車業界の未来を象徴する4つのキーワード「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared&Services(シェアリング&サービス)」「Electric(電動化)」の頭文字を組み合わせた造語で、新しい車の開発で核となる考え方を表したものだ。SDVはこれらの要素を効果的に実現・統合するためのひとつのアプローチとされている。
OTAはOver The Airの頭文字をとった造語で、無線通信を活用して遠隔から車両のソフトウェアやファームウェアを更新・管理する技術のことだ。SDVの概念において、OTAは中核的な役割を果たす。車両のソフトウェアを無線でアップデート・改善することで、メーカーは新機能の提供や不具合修正、セキュリティパッチの適用を迅速かつ効率的に実施できる。また、車両の価値が時間とともに向上し、ユーザーエクスペリエンスの継続的な改善が可能となる。
技術課題の解決や、市場の動向を読み解くには?
誰も教えてくれない情報収集の基礎
「情報収集の教科書」を見てみる
Stratistics MRCが2024年11月に発表したレポートによると、SDVの世界市場規模は2024年に516億4,000万米ドルに到達。2030年には1,549億6,000万米ドルまで伸長すると予測している。
また、SDVの市場シェアでは、大幅な技術向上と顧客基盤の拡大によって、今後は中国、日本、インド、韓国といったアジア太平洋地域がイニシアチブをとると予想。
一般社団法人電子情報技術産業協会の調査では、SDVは2035年時点で6,530万台がグローバル市場に投入される見込みで、世界の総新車生産台数の66.7%を占めると推測している。
一方、日本では2024年5月に経済産業省と国土交通省が「モビリティDX戦略」を連名で発表。同戦略はSDVを強く意識した内容になっており、2030年および2035年までに「SDVのグローバル販売台数において日系シェア3割を目指す」との記載がある。
漠然とした市場調査で終わらせない!
業務に活かすための市場調査のやり方とは?
「市場調査の教科書」を見てみる
SDVが普及することで、ユーザーそして社会に多大なる恩恵がもたらされる。代表的なメリットとしては、大きく以下の3つに集約される。
OTAによって車両購入後も新しい機能の追加や既存機能の改善が行われるため、継続的な性能向上が期待できる。また、OTA技術によって遠隔で空調などの車内環境を調整することも可能となる。
アクセルやブレーキの感度、ステアリングの重さ、車内のディスプレイや操作パネルのレイアウトや表示情報の変更、音響設定、車内照明の色など、個々のドライバーの好みに合わせて設定が可能となり、より快適で安全なドライビング体験が実現される。
車両の機能やサービスをソフトウェアで提供・更新できるため、特定の機能やサービスを月額や年額で利用するサブスクリプションモデルの構築が実現可能となる。また、ユーザーの行動や車両の状態を分析・収集することで、保険やメンテナンスなど個別化されたサービスの提供もできるようになるだろう。
技術課題の解決や、市場の動向を読み解くには?
誰も教えてくれない情報収集の基礎
「情報収集の教科書」を見てみる
ネットワークを介して統合的に制御する性質上、セキュリティリスクやソフトウェアの複雑化といった新たな課題や問題点と向き合わなければいけない。
先に述べたように、ソフトウェアが複雑化・高度化することで車体の機能性は確実に向上するが、外部からの不正アクセスや攻撃のリスクが増大することは避けられない。デバイスとの接続が複雑化するほど、ネットワークを介して他のデバイスなどにも影響が波及するため、SDV普及において懸念すべき課題として想定されている。
従来の車両では、エンジン制御やブレーキ制御など特定の機能ごとに独立した電子制御ユニットを配置する分散型アーキテクチャが採用されていた。そのため構造は複雑化し、車全体の送付とウェア規模が航空機を上回ってしまったほどだ。この車両システムの複雑化を解決するために、昨今ではSDVでは車両全体を統合的に制御する中央集権型のシステムへが主流となりつつあり、そのための開発が進められている。
頻繁にソフトウェアのアップデートが行われるようになると、全体の挙動を正確に予測・管理することが困難となり、システム間の干渉や誤作動が発生するリスクが高まっていく。最悪の場合、車両の機能面に直接的な影響を及ぼし、交通安全上の重大な懸念となってしまう。SDVを安全に普及させるためには、技術的な検証プロセスの導入と法整備の両面からのアプローチが不可欠といえる。
要件を満たすための技術課題をどう解決する?
研究開発、製品開発のための情報収集のポイントとは?
資料(無料)を見てみる
最後に国内外でSDVを開発する企業やメーカーの取り組みや開発動向について紹介したい。
トヨタは、ソフトウェアスキルの向上を目的にデンソー、アイシン精機と共同出資で2018年3月にTRI-AD(現:ウーブン・バイ・トヨタ)を設立した。SDVのプラットフォーム「アリーン(Arene)」の開発をスタートさせ、2025年に実用化、2026年に発売される次世代EVから実装される予定だ。
2024年の佐藤社長の決算発表では、SDVの基盤づくりを推進するため、自動車産業を超えた戦略的パートナーシップの構築に取り組む予定であることを明らかにしている。
実際に、同年10月にはNTTと「モビリティAI基盤」を共同で構築することを発表。今後両社で2030年までに5,000億円規模の投資を見込んでおり、2028年頃からさまざまなパートナー企業と社会実装を開始、2030年以降の普及拡大を目指す。
技術課題の解決や、市場の動向を読み解くには?
誰も教えてくれない情報収集の基礎
「情報収集の教科書」を見てみる
テスラは、2012年にアメリカ、2014年に日本といち早く実用化を進め、まさにSDVの先駆け的存在だ。各車両から得られる走行データやユーザーの操作情報を分析することで、自社の自動運転技術であるFull Self-Driving(FSD)の精度向上や、新機能の開発に役立てている。
また、車内エンターテインメントやインターネット接続などの機能もソフトウェアによって制御されており、ユーザーのニーズに応じて柔軟にアップデートやカスタマイズが可能である。これらの取り組みは、SDV特有のソフトウェア中心の車両開発や新しいビジネスモデルの可能性を示し、自動車業界全体に大きな影響を与えた。
ホンダは、2024年3月に日産と自動車の知能化・電動化時代に向けた戦略的パートナーシップの検討を開始。同年8月には次世代SDV向けプラットフォームの領域における基礎的要素技術の共同研究を開始することを発表。さらに、三菱自動車とのパートナーシップも発表した。
2024年12月には日産との連携を深めるため、経営統合に向けた検討が執り行われていたが、2025年2月に協議は打ち切られ、白紙となった。この事態は、先に述べたパートナーシップにも影響を及ぼすことが考えられ、今後の戦略が大きく転換する可能性は高い。
技術課題の解決や、市場の動向を読み解くには?
誰も教えてくれない情報収集の基礎
「情報収集の教科書」を見てみる
SDVは、モビリティのあり方を大きく変える可能性を秘めた技術のひとつだ。市場規模は年々拡大し、主要な自動車メーカーやテクノロジー企業がこぞって開発に参入しているが、一方でソフトウェアの複雑化やセキュリティリスクなどの課題も浮き彫りになっている。より安全で利便性の高いモビリティ社会を実現するためには、産業全体での共創と継続的な技術革新が不可欠だ。SDVの進化は、自動車を単なる移動手段から、よりインテリジェントで柔軟なデバイスへと変貌させるものであり、今後も動向を注視したい。